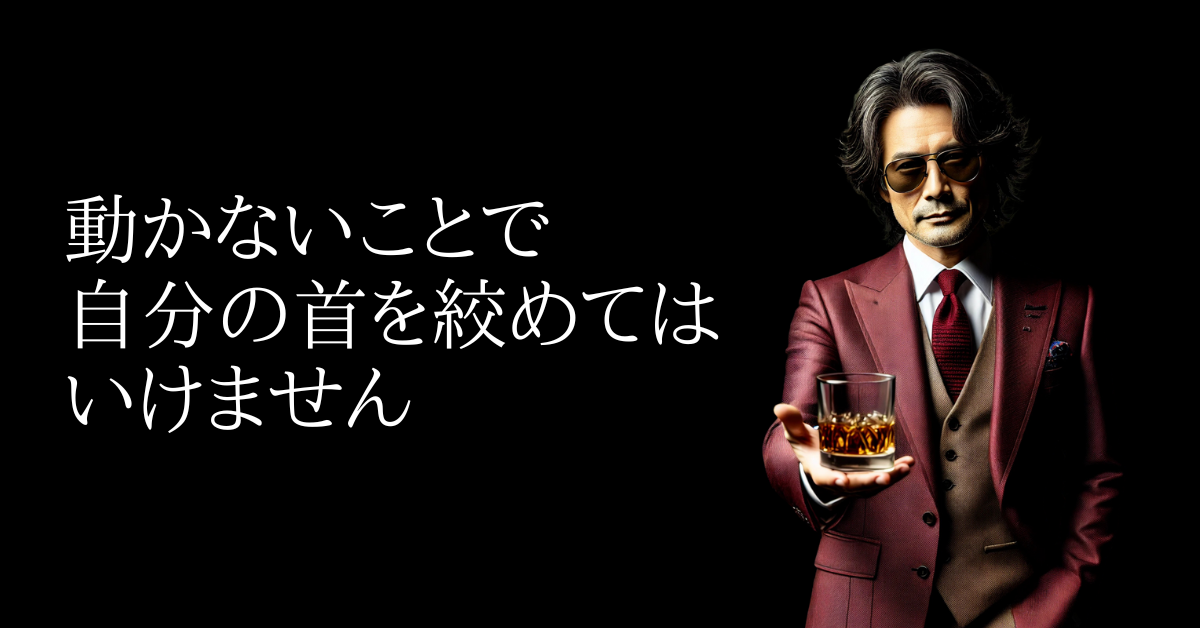「コンプライアンスを守れない企業は淘汰される。」
こんな言葉、聞いたことがあるのではないでしょうか?もちろん、コンプライアンスは大事です。しかし、必要以上に「コンプラ、コンプラ」と言い続けていると、中小企業は間違いなく息切れを起こします。なぜなら、コンプライアンスを徹底することにリソースを注ぎすぎると、肝心の成長戦略や収益向上に手が回らなくなるからです。
守らなければいけないものは守るべきです。しかし、全てを律儀に守ることが本当に正しいのでしょうか?その答えは「ノー」です。守らなくてもいいルールを過剰に意識することで、企業の自由な発想や攻めの姿勢が損なわれるケースが少なくありません。
コンプライアンス至上主義の罠
守りに入る企業が陥るジレンマ
中小企業が全ての規則やガイドラインを100%守ろうとすると、どうなるでしょうか?例えば広告の運用では、コンプライアンスガイドラインを重視しすぎて、結果的に目立たない広告しか出せなくなるケースがあります。「クリーンすぎて誰にも刺さらない広告」が良い結果を生むでしょうか?
実際に生じるコスト
規則を守るにはコストがかかります。法務チェック、追加の審査プロセス、社員教育…これらすべては時間もお金も必要です。それを全て満たすためには、収益性や競争力を犠牲にすることも避けられません。
守らなくても良いルールに足を取られる
守るべきルールと、そうでないルールの切り分けができていない企業は、不要なリソースを費やします。例えば、業界の慣例として存在する曖昧な規制や、実質的に義務ではない推奨事項まで厳守しようとすることで、他社に後れを取る場合も。
成功企業が実践する「コンプラのさじ加減」
守るべきラインを見極める
成功している企業は、何を守るべきで何を守らなくても良いか、冷静に判断しています。例えば、大企業向けのガイドラインをそのまま中小企業が取り入れてしまうと、過剰な対応に陥ります。必要なのは、自社のスケールに合ったルールの解釈です。
リスクテイクの重要性
コンプライアンスを重視する一方で、リスクを取る勇気も欠かせません。特に新しいチャレンジをする際には、多少のリスクは避けられません。守りすぎることで得られる安心感と引き換えに、成長機会を失う可能性もあります。
具体的な例で考える「過剰なコンプライアンスの影響」
広告運用における制限の弊害
例えば、LINE広告の運用を考えてみましょう。コンプライアンスを理由に広告文言やクリエイティブを無難な方向に寄せすぎると、他社との差別化が難しくなります。競争の激しい業界では、これが命取りになることもあります。
商品開発での足かせ
新商品を開発する際にも、あまりに多くのルールを意識しすぎると、斬新なアイデアが埋もれることがあります。過剰な社内審査や外部チェックによってスピード感を失い、競合に先を越されるケースも珍しくありません。
中小企業が取るべき具体的アプローチ
守りと攻めのバランスを取る
重要なのは、「守り」と「攻め」を適切にバランスさせることです。コンプライアンスを無視するのではなく、守るべき部分を見極め、リスクを許容できる範囲で攻めの姿勢を持つことが求められます。
最後に
中小企業にとって、全てのコンプライアンスを徹底することは、時に成長の足かせになります。「ルールは守らなければいけないもの」として捉えるのではなく、「自社の成長を支えるための指針」として活用する視点が重要です。
守るべきものを守り、時には攻めの姿勢を持つこと。これこそが、中小企業が生き残り、さらに成長するための鍵なのです。「コンプラコンプラ」と言い続けることは簡単です。しかし、企業が真に取るべき行動は、その一歩先にあります。