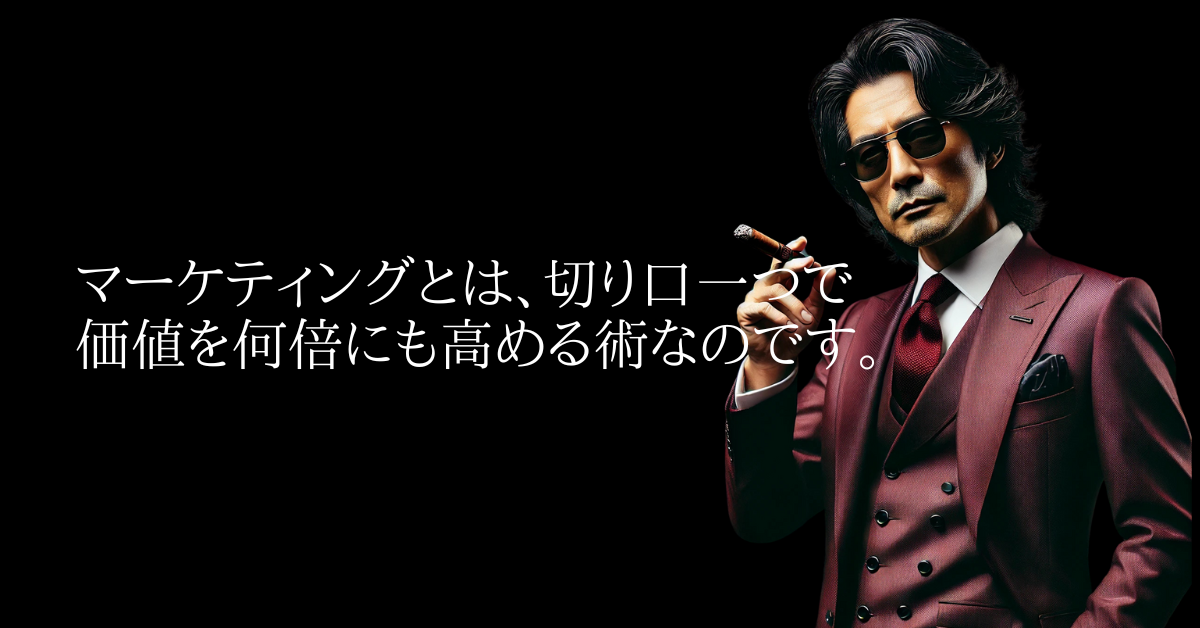切り口次第で伝わり方は変わる
商品やサービスの良さを語るとき、多くの人が「メリット」にフォーカスしがちです。しかし、そのメリットが具体的にどのような「ベネフィット」をもたらすかを明確に伝えなければ、顧客には響きません。それどころか、顧客はその価値を理解できず、行動につながらないこともあります。
たとえば、Google Mapのレビュー評価を上げることは「メリット」に見えます。しかし、それが「インバウンド集客につながる」「旅ナカ顧客を取り込む」というベネフィットを紐付けることで、価値が具体化されます。この違いこそが、マーケティング戦略における「切り口」の重要性を物語っています。
では、なぜ「切り口」を変えることが重要なのでしょうか?それを理解するために、次章以降で解説していきます。
顧客視点で考える「メリット」と「ベネフィット」の違い
多くのマーケターが「商品の強み」を軸に訴求するのは当然の流れです。たとえば、以下のような表現が一般的です。
- 高速で動作するツール
- 見やすいレイアウトのダッシュボード
- 低価格なプランの提供
これらは確かに商品の「メリット」を表していますが、顧客にとっての具体的な利点、つまり「ベネフィット」が見えてきません。顧客は「このツールを使うことで、時間がどれだけ節約できるのか?」や「この低価格が自分のビジネスにどう影響するのか?」といった疑問を持ちます。
ベネフィットは、「顧客にとっての恩恵」を具体化する作業です。例えば、「高速で動作するツール」を「日々の作業時間を30%短縮し、他の業務に集中できる」と言い換えることで、顧客の目線に立ったコミュニケーションが可能になります。
切り口を変えるとはどういうことか?
切り口を変えるとは、一つのメリットを複数の視点から捉え直し、それぞれのベネフィットに結びつけることです。
Googleレビュー評価向上の場合
- 視点A:購買行動
ベネフィット:インバウンド旅行者の集客率を20%向上させる。 - 視点B:ブランド信頼度
ベネフィット:新規顧客だけでなく、地元住民からの信頼度も上がる。 - 視点C:競合との差別化
ベネフィット:評価を改善することで、競合店舗に差をつけられる。
同じ「レビュー評価向上」というテーマでも、切り口を変えることで訴求力の高いメッセージを複数作成できます。
なぜ「切り口」が必要なのか?
切り口を変えないと、顧客にとっての課題が解決されません。特に、専門用語や業界特有の知識が前提となる場合、顧客は「メリットが自分にどう関係するのか」を想像できません。これが、「切り口」の重要性を裏付ける理由です。
具体例で見る「切り口」の威力
以前、インバウンド集客に課題を抱える飲食店向けにGoogleレビュー対策を提案しました。当初、クライアントは「レビュー評価の向上」がどのように課題解決に繋がるのかを理解していませんでした。
そこで、「旅ナカ顧客の購買行動」という視点から「現在地付近のお店を探す際にGoogle Mapが使われる」ことを説明し、「レビューが購買行動に影響する」という切り口でアプローチしました。結果、クライアントは評価改善に前向きになり、集客率が目に見えて向上しました。
「切り口」を見つける3つの質問
切り口を探す際、以下の質問を自分に投げかけてみてください。
- このメリットが顧客のどんな課題を解決するのか?
- 顧客にとっての具体的な恩恵は何か?
- 競合商品と比較して、どの点で優れているのか?
これらの問いに答えることで、新たな切り口が見えてきます。
切り口を変える具体的なテクニック
切り口を変えるための手法として、以下を試してみてください。
- 仮想顧客インタビューを行う
顧客の視点に立つことで、見落としていたベネフィットが浮かび上がる。 - 競合商品の分析
競合の強みを逆手に取り、自社商品のベネフィットを際立たせる。 - データで裏付ける
数字を使うことで、顧客の理解が深まる。
マーケティングにおける「切り口」の未来
デジタル時代において、切り口の多様化はますます重要になります。AIが生成したマーケティングメッセージが増える中、人間らしい切り口を見つけることがブランドの差別化に繋がります。
切り口が変われば世界が変わる
切り口を変えることで、顧客への伝わり方が劇的に変化します。一見すると些細な違いに見えても、それが成約率や顧客満足度に大きな影響を与えるのです。たとえば、レビュー評価を「集客の武器」として捉えるか、「ブランディングツール」として捉えるかで、マーケティング戦略の方向性は大きく変わります。